 | エジプト人 | 
|
|---|
| ミイラ医師 シヌヘの 全版 映画EGYPTIANの原作 全巻版が手に入ったので読み直しました。 前回読んだハイライト版はほんの触りぐらいの内容でした。 後半で、主人公のシヌヘの出生が分かる部分がない為に、最初に彼がが葦の船で流れてくる シーンを抜いていたようです。 アケナテン〜ホルエムヘブ王までの治世年間の出来事をうまく織り交ぜて書かれた作品で、 書かれた当時の古代エジプトの一般常識が十分に盛り込まれた作品だと思います。(現在では否定される部分もあるが) 読んでいて一番感じたのが、マンガなどに随分引用されているのだという事です。 頭部切開治療での止血師とその後の儀式での見せかけの処刑で死んでしまう 部分は、山岸涼子の「ハトシェプスト」に。 芸術家トトメスが幼少時代、王宮の医師の泥酔した姿を描く部分は、「ナイルのほとりの物語」にカエムワセトが布袋様を作る場面にアレンジ。この本の場合は、全く同じ時代を描いているためか、引用(またはヒント)している部分が多いですね。
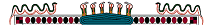 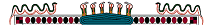 アケナテンの出生 王妃タイア(ティイの事です。原文のスペルが分かりかねますが、訳の違いかもしれません)が結婚して22年に初めて男子を出産したとなっています。 この男子、つまりアケナテンの前に、実際はトトメスという夭折した長子が居たことが分かっています。 但し、この本が書かれた1945年に知られていたかどうかは?ですが。 尚、王家DB350のカシェで発見されたドケットの無い3体のミイラのうち、若年の髪房をつけた少年のミイラは この夭折した長子トトメスではないか?と する設もあります。横にいる老女の髪がツタンカーメンの遺物から出た髪と 血液型で一致する(DNA鑑定はされていない)その横にあったことかららしいのですが。(他にも年齢とか あるのでしょうけれど)尚、その横に居た女性のミイラが、2003年6月にネフェルティティではないか? とされたものです。(但し、こちらは正式な報告書では性別の判断不能、年齢18〜35とかなり怪しい) テーベの太陽神 テーベの主神はアメン神ですが、文中は太陽神が連呼されます。確かにアメン・ラーという太陽神ラーと習合した神はいますが。 原文でどう書かれていたのか気になる所ではあります。 尚、ここでは「生命の家」と「死の家」がテーベの太陽神の境内にあったとしていますが、「生命の家」は確実にあったと思われますが、「死の家」が神殿にあったというのは全然聞かないのですが… バケタモン 本文では、タイア(ティイ)の最初の娘でアケナテンの姉となっています。 後半にホルエムヘブが王位を得るため結婚する事になりますが、そうすると相当の歳だったんでは・・・ これはティイ王妃の末娘バケト・アテン(ベケトアテンとも)の事と思われます。 アケナテンの治世12年のレリーフに幼女として表現されているので、歳はともかくアケナテンよりは年下であるのは間違いありません。 また実際にホルエムヘブが妃としたのはネフェルティティの妹と言われるムトネジェムト。 尚、文中では石を持ってきた男と寝て、その石で建物を建てる話が出てきますが、これはヘロドトスの歴史からの引用ですね。 その他もろもろ 銅貨を出し合って… エジプト国内の話ではないのですが、貨幣経済ではまだないのでは?と思うのですが。 タニスよりシナイを経て 一応、タニス(古名ジャネト)は第21王朝が開始したという事だそうなのですが… 紅を塗った口元 書籍類を見ると、口紅は塗らなかった というのが主流のようですが。 ヒッタイトに王子を要求したのがバケタモン姫 誰が送ったか名前は不明ですが、「王妃」という事だそうですが。 ネフェルティティは司祭エイエの娘となっているが、歴史ではミタンニ国王トウシェラッタの王女ネフェルティティが嫁いできたことになったいる 訳者の後書きですが、トゥシュラッタの王女タドウケパ(ダキトパなどとも)がネフェルティティ(やってきた美女)というのは以前は主流だったようですが、最近はアイ(文中のエイエ)の娘とする説が主流の様です。ネフェルティティの像の乳母がエジプト人だった事など理由があるようですから。となると、かなり先見の目があった? 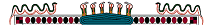 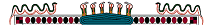 エジプト人 作 ミカ・ワルタリ 訳 飯島淳秀 角川文庫 |