 | 小説・漫画の落とし穴 | 
|
|---|
とくに文字だけの小説(挿絵を描くのは本人ではありませんし)に比べ、
漫画の場合 衣装や背景(建物や風景)を描くため、あり得ない風景が登場する事になってしまったりします。
又、そのとき使った資料(書籍)によって、左右されてしまう事も。
著者によっては全く違う事を書いてあったりしますし、
後の発掘資料などで『定説』が置き換わる可能性もありますから。
ロシアバレエ団が日本の竹取物語を上演した時に、男性ダンサーが
いかにも足袋風に足の内側に短い黒い線を数本…コハゼの模様をつけていました。
見たときは「足袋だぁ〜」と思ったのですが、足袋について調べると
|
・初期の足袋は指が分かれていない(つまり現代の靴下と同じ) ・初期は足首を紐で縛った(ゴムのないルーズソックス状?) ・コハゼは明治になって出来たもの |
気づいた次第です。平安時代でも、その年代によって足袋の形状も異なるし、同様に
男子の被る冠や衣装も 初期はホーム着だったのが、後に公式の場でも着ることになったり
とややこしいです。本格的に突き詰めるとあり地獄のようです。(笑)
古代エジプトも同じようなものなのですが…
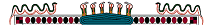 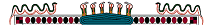 馬について 現代人の間隔なのか、騎馬=馬に乗る という情景が書かれています。 まず、馬が入っていたのはヒクソス(第2中間期 B.C.1800〜1550)時代とされるので、それ以前の話であれば、馬の登場自体が×。一度絶滅して、後から入ってきたとするにしても、先王朝時代の遺構に馬が出てこないのでかなりキケンな想定になります。 馬に乗る のも古代エジプトでは稀な事とされるので、ペルシア統治以降(主にプトレマイオス朝)などでない限り、馬に乗ってしまうのは良くないでしょう。 2003.07.30追記 エジプト・オリエント学ではなく、動物学関係の本をたまたま借りてよんだのですが、 エジプトにおける馬は馬にあらず、馬と驢馬のあいの子である騾馬が多いのだとか。 その本では、エジプトでは 雄馬は戦車を引くため 雌馬は乗馬用 とありましたが、どの時代の事をさしてなのかが記載していなかったので、古代の事なのかどうかが不明。 テーベの新王国時代の女性の墓から、鞍などが出土していると記載も見ました。 でも、書籍を明後日も見つからないのですょ・・・ 故意に隠されてる?(笑) ベッドについて 古代エジプトのベッドはベッドボード…現在は頭の部分にある板…が足下の方にあります。 その為、漫画などではどうしても現在の構造になっている事が多いようです。 余談ですが、墓地から発見されるドレーパリー(サリーの様に1枚布を身体に巻いて着る服)は、シーツと分類される事もあるそうです。その違いを判断が難しい事と、どうしても身近にある類似品に置き換えてしまうからでしょう 陥り易い地名の落とし穴 古代エジプトを描く、書くとすると都市名にはちょっと複雑な問題が絡んできます。 古代都市には A.所在地も古代の都市名もわかるもの B.都市名は資料(パピルスや碑文)にあるのに、その場所が定まっていないもの C.遺構が発掘されたが、名前がわからない都市(便宜上現在地名で呼ばれる) 大別で以上の3種類に分けられると思います。Aは更に 1.古代エジプト語での都市名が分かる。 2.古代エジプト語とギリシア語での都市名が分かる。 3.ギリシア語名しか分からない。 に分けられると思います。しかも、実際は遺跡名として、現代語名…例えば アケナテンが遷都した新王都アケト・アテン(アテンの地平線)は、アラビア語での地名テル・エル・アマルナ…で呼ばれる事がほとんどです。 さて、遺跡地図を見た時に、そこに描いてある都市名は、アラビア語がほとんどで、ギリシア語が稀に描いてあったり、古代エジプト語は()などでくくられていることが多いです。一つの都市でも時代と共に名前を変えているもの(日本でも江戸→東京などもあります)や、後から築かれた都市が現在の都市などと混在している状態になっています。 ただ、都市というものは、町として存在し続けるには条件が必要なわけで、例えば古代エジプトなら ナイル増水期でも居住地が水没しない、耕作地となる場所が周囲にある、乾燥期でも生活水に困らない などある程度の条件が必要になるので、タニスのように21王朝に造営されたとされる都市でも、その元になる都市(石造りの神殿と異なり、泥レンガつくりの村のような遺構が残りにくいもの)が基盤としてあったのではないか?という想像もできなくはありません。 アケト・アテンは破壊されたものの、遺構の残りが良いのは後代にその上に都市が築かれなかった故で、それ以前も都市がなかったところから あまり立地条件の良い場所ではなかったのでしょう。 だらか、末期王国時代の都市で、新王国時代存在しなかった都市でも、村ぐらいはあったでしょうし、水が得られないなどのことが無い限り、後にも先にも人が全く住まないという都市は少ないでしょう。 とは言っても、その時代時代にみあった都市しかなかった筈なのですが…。 地図・地形 小学生ぐらいの時に、輪郭だけの地図に都市名を書きこんだりする白地図というものがありました。 古代エジプトは現代から5000年〜2000年前の時代なので、地図は現在のものとその輪郭(海岸線)が異なるのは確実です。スエズ運河だってありませんし。そのスエズに先行した運河も時代によって砂に埋もれたり、ルートが違って作っていたりと時代によって異なります。またそれによってその沿岸にあった都市もあったりなかったりする訳で… 又、現在でも河口付近というのは土砂が堆積し、陸地部分が海に広がる、又波の浸食などで砂浜などが侵食されて狭まるなど地形が変化しています。 古代エジプトにおいても、ナイルの支流のうち ペルセウム支流(この支流に沿ってヒクソスの首都アヴァリスがあった)は、新王国末期には枯れてしまっています。(支流の名前からもっと後代に枯れたようにも思えるのですが…) リビアよりにあったカノプス支流も現在はないですが、カノプス容器の由来などから、ローマ時代までは存在していたと思われます。 又、シナイとの境目、現在のスエズ運河付近にあった巨大な塩湖もプトレマイオス朝には干上がったそうですから、古代エジプトの中でもその地形はかなり変化しています。 つまり・・・ 参考にした資料の地図を見たとき、それが 現在の地図に(遺跡としての)都市名を載せたもの 当時の状態の地図に(現在も含めて)都市名を載せたもの 当時の状態の地図に当時の都市名だけを載せたもの で随分違う状況になると思います。 特に、デルタ地帯は遺跡・遺構が多く(故に私が作った辞書上の地図は隙間も無いほど文字だらけになっていて、訳がわからなくなっている)、初期王国時代の都市〜ローマ時代まで一緒くたにされているのがほとんどなので、100%混乱します。 |