 | ナイルのほとりの物語 | 
|
|---|
トト神官にして魔法使いのラーメスが時空を越えて関わる、古代エジプト(〜ギリシア時代まで)様々な物語。
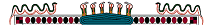 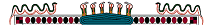 不機嫌な姫君 基礎となった話はヘロドトスの「歴史」だったかにあった話だったと思います。 時代は不明ですが、カラシリスを来ているので、新王国時代以降、但し、州の太守の娘が王妃の禿鷲の冠を付けるのはかなり大胆な… 水中に落としたブレスッットを拾うために水を裂いた魔術は、ウエストカーパピルスによるもの。 運命の王子 筋としてはありがちな怪異譚風なのですが、これまた時代が不明ですが、カラシリスを来ている所から新王国時代以降か。本来の話は、パピルスは欠損している為、最後がどうなったのか分からない という事です。 領主の娘…がウラエウスを付けちゃって良い物やら… ここだけではないのですが、吹き出しなどが現代のネタ(シュワちゃんがタイプ など)になっているのはご愛敬。 イシスの涙 ナイルの増水については、神話ともども色々あるようですが… 中州にあるムテ島のイシス神殿。イメージはフィラエ島のイシス神殿でしょうか? 背景にローマ時代のキオスクが出てくる事から、プトレマイオス王朝ではないかと。 星の砂漠で見る夢は 最後の9〜11巻になるとアンクティファがだれなのやらとこの謎が分かるのですが… 服装からして、こちらも新王国時代以降か。 ちなみにオンというのは聖書の表記。古代エジプトではイウヌ、ギリシア語ではヘリオポリス。 死者の書 ツタンカーメンの死の真相というべき話。 アンケセンナーメンの殺害説というのも実は存在するので、奇をてらったものではありませんが。 王宮が神殿のような形状であり、ベッドと枕が・・・ メンネフェルからの手紙 トトメス3世VSハトシェプスト、トトメス3世の母の話…という事ですが、トトメス3世の母はシシィでなく、イシス。 それと、メンネフェル(現在のメンフィス)は、本来はイネブ・ヘジ。メン・ネフェルは正確にはペピ1世のピラミッドを差していた言葉。いつからメンフィスの由来になったかは不明ですが。 とにかく、メンネフェルにしたのなら「テーベ」もワセトにして欲しかったですネ。 この悪女ではない、ハトシェプストの描き方は、割と好きですが。 精霊の島 オペラ「アイーダ」をマンガにしたもの。 アイーダではなく、イルディアというのは、ヌビア王朝のアメンの神妻「アメン・イルディス」からもじったのでしょうか? 父(オペラではアモナズロ)ではなく兄が出てくるのがオペラと異なる点ですが、それ以上にアムネリスならぬメリエトがプライドが高いものの賢女なのが面白い。結構オペラでは無視されている25〜26王朝の状態がちゃんと描かれているのと、最後の海に流れているのは手塚治虫の火の鳥のエジプト編の影響か? 最後にトト神官ラーメスがヘロドトスに語っているシーンがありますが、このころのヘロドトスはかなりリアル。 夢解き-ヨセフの物語- 聖書の出エジプト記の前、創世記の第37章〜47章の部分。 エジプトのパロ(ファラオ)をヒクソスとするのは面白いのですが… となると、19王朝のセティ1世+ラムセス2世じゃなくても、上エジプトからヒクソスを追放した、18王朝のファラオ自体もヨセフの事は知らないのよね。(笑) エクソダス 内容は、聖書の出エジプト記の前半で若き日のモーセがエジプトを出るまで。 出エジプト記のパロをラムセス2世に設定した二人のラムセスの話に史実のカディッシュの話も混ぜてある。 後に出てくる「黄金の地平線」の後に続く話。 王妃ネフェルタリを姉としていますが、ネフェルタリが姉弟だったかどうかは・・・ アキレウスの遺産 アレキサンダー大王の東方遠征中のシーワ・オアシス。ギリシアの方は良く分かりませんが… 半月の月の形が日本風。(エジプトは緯度が異なるため、角度が違う) カエサリオン クレオパトラをギリシア人風に、アントニウスとの子供達も少しだけ描いてある珍しいかも。 ファハカ叙事詩 上王国と下王国で争っている中間期ですが、王子ファハカの父が無惨な殺され方(タアア2世)とキアンというヒクソス系の名前から第2中間期を意識したものと思います。将軍の名前もヒクソス系だし。 母親は、映画「エジプト人」に出てくるネフェルネフェルネフェルみたいな感じですが、最後に王宮の隠し部屋が砂に埋もれるのは、やはり映画「ピラミッド」からか… 黄金の地平 5〜7巻と3巻(正確には2巻半分)に跨っているのでこの本では2番目に長い作品。 2巻に出てくる死者の書の前に繋がる、アケナテン時代の話。 オリジナルだと思っていたのですが、ミカ・ワルタリのエジプト人からの引用(応用)がとても多い。 尚、アメンヘテプ4世事アケナテンの妹でティイ王母に育てられているムテムイアは、本来はアメンヘテプ4世の父アメンヘテプ3世の母でミタンニの王女の名前。ホルエムヘブが王位を得るために結婚するのはムトジェネムト(ネフェルティティの妹とされる)。 尚、このマンガではティイ王妃は下エジプトの漁村の生まれでアムル国へ行きそこで産んだ子が話の中心のアイザック。ティイが漁師の娘というのは上述のミカ・ワルタリの本でしか見たことがありません。 本文では、その後エジプトと内通し、アムル国が滅びた時王の目にとまった という設定をしていますが、実際にはティイの両親がアクミムの神官(アクミムは割とテーベに近い上エジプトの第9ノモスの州都)であったとされているのと、アムール州自体、アケト・アテンに書簡を送っている事から、滅亡してはいなかと。アメンヘテプ3世は軍事遠征自体初期には行っていますが一国を滅ぼすほどのものでは無かった筈です。上述のミカ・ワルタリの本にもアムール州が滅ぼされる様が描かれているのでその影響が大きいかと思いますが。 このマンガの絶対的主人公?ラーモセが殆ど話にからんでこない作品。 聖家族 イエス生誕をテーマとしたもの。 黄金の地平線と異なり、かなりラーモセがからんで来る作品。 アアンソル奇譚 ついにラーモセ現在に出現?(笑) 遺跡で古代の話をする というモチーフ。二人の兄弟の物語を主軸においているが、アヌプ、バタではなく、ウシルマリ王(サトニ・ハームス物語のエジプト王の名前)、アハト、アヌプの妻と神々が作ったバタの妻を同一人物にして描いています。 ウシルマリ王にエジプトから献貢してくるとは… 金と銀の翼 上下エジプトが分かれている、「珍しい」馬が出てくる事から第2中間期の様なのですが、統一した後の都がイチ・タゥイという事から第1中間期の話。 文中出てくる下エジプト王ホル・アハは実在の王ですが、初期王朝である第1王朝のファラオ、又、イチ・タウイに都を移したのはアメンエムハト(1世)で、父の名がセンウセルトまでは良いのですが、母ネフェルトはエレファンティネ島の出身で下エジプトの王族じゃぁないんですね。 天空の神話 主人公?たるトト神官ラーメスが何故時空をさまよう事になったのか を描いたもの。メソポタミアまで話が広がるかなり特異な話になっています。 最後の最後で、話が急ぎすぎの感じがありますが。あれだけの魔力?を持つヘテプヘレスが松明の火でいとも簡単に焼けちゃう事には「?」です。いわれのある聖なる火とかならともかく。 この話の中で、ラーメスはクフ王の息子と言うことなのですが… クフ王の息子達 長子としてクフカフ(即位前に絶命)その妻でクフの第一王女のヘテプへレス、その娘メルサンク。 他にクフの息子として カフラー、ラーメス、ラージェデフ、王女のアンクティファ。 ラージェデフがヘテプヘレスの後夫(?)として即位、その後、カフラーがメルサンクを妃として即位になっています。 実際には…まず、クフ王の後にジェドフラーが即位(筆記上、神の名前は尊敬の倒置として、一番前に書くので、ラージェデフと読んだ可能性がありますが、一般的にジェドフラーの方が知られているかと思います。) 妃はヘテプヘレス(2世)で息子セトカと娘ネフェルヘテプが居ます。 その後、カフラー王が即位。妃はメルサンク(3世、ヘテプヘレスとカワブの娘)とカメレルネブチ(クフ王の娘)。 クフ王の王子としては、カワブ(カーウアブ)、ジェドフラー(ラージェデフ)、カフラー、クフカフ(クフカェフ)。娘はヘテプヘレス(2世)、メルサンク(2世)、カメレルネブチ(1世)。 クフカフは実際にもクフ王の息子ですがクフではなく、カフラー王の宰相。カフラー王の妃メルサンク(3世)の父のカワブはクフ王の宰相をしていました。 と、いう事は、まんがの長子のクフカフは、恐らくカワブで、本来のクフカフは描かれていないと見るべきでしょうか。 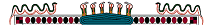 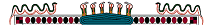 ナイルのほとりの物語(全11巻) 長岡良子 秋田書店
|