 | 王家の紋章 | 
|
|---|
| この漫画は冊数が多い(いまだ連載中)だけに、あげらたらきりがないぐらいあるのですが… 新王国時代を謳っているので、それを基準とすると時代錯誤の場面もしばし見られます。 特にエジプト国内に留まっている時はアラが出やすいので気が付く話題が豊富です。 尚、あくまで考古学上の定説などですので、今後の発見次第では、漫画の方が正しい事が判明したりして!?
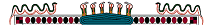 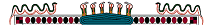 鉄の鍛錬 追記 03.12.04 3巻でキャロルが鉄の作り方を白状しない(ヒッタイトの)捕虜の拷問を阻止する為、自ら鉄の刀を作ります。現代人であるキャロルが博識=古代の人から見ると神の娘である事の象徴的シーンで、あまり気にしていなかったのですが… 冶金技術関連の本を読んでいて、実はおかしい事に気づきました。 キャロルがやっているのは、製鉄でなくて、鍛鉄。鉄は錆びやすい事もあり強い金属ではなく、鋼(はがね 鉄に炭素を付加する)にしないとその特性が活かされないそうです。 さて、ここでは既に剣の形に鉄を作ってあります。 ヒッタイトの捕虜はここまでは教えたとしても、このマンガでは「古代書ではエジプトは鉄を産出しなかったってあるけど(45巻)」とあるので、まず鉄の原料の鉄鉱石を何処で調達したのかが問題になります。 そして、キャロルは鍛えられていない鉄の剣を「かなばさみ」で持っていますが、古代ではこれが無いため、鉄の鋳造を難しくしていたそうです。鉄の融点は1530度。エジプトでポピュラーな銅の融点は1080度。その差500度なので、(溶けていないにしても)持ったら溶けてしまう可能性大なのですが。それと鉄に対応した炉の作り方まで一人の捕虜が知っていたのか?という問題もあります。(鍛冶屋は炉まで作らないし) 鉄の鍛え方は近代では簡単ですが、古代では焼き戻しと焼きなましの二通りの方法があります。焼き戻しは何度か焼いて硬化させる方法で、焼きなましは焼きと冷却を交互に行う方法。キャロルが実践したの後者ですが、早くてもB.C.500年頃になってから開発されたらしく、ヒッタイトが知っているとは思えません。又、この技術はその温度管理が難しいので、古代では失敗も多かったとか。実際に古代で使われて居た方法は錬鉄。炭を溶かし混ぜて作る様なもの。所が、これ、青銅よりも弱いのだそうです。 エジプトが鉄器時代に入ったのは、B.C.600年頃で、それまでは「黒い銅」などと銅と鉄の区別が出来ていなかったとか。 で、エジプトの鉄鉱石の出土域があるのですが、案外多いです。 シナイ半島 … チタン、マンガンを含む良質の鉱山 東方砂漠 …… 含鉄石灰岩、赤鉄鉱、褐鉄鉱など5カ所 西方砂漠 …… カルガ・オアシス、バハリヤ・オアシス ファイユーム… マンガン鉱 アスワン …… 赤色オーカー、磁鉄鉱など数カ所 デルタ ……… マンガン鉱 カイロ近郊 … 黄色オーカ ワディ・ハンマート 採掘しつくされている シリア方面 ……高品位の鉱床は少ないが低品位の鉱床は非常に多い。 行動怪路 古代エジプトに戻ったキャロル(25巻)が、ナイル河口の漁村からマシャリキにムサの山へ連れて行ってもらうのですが、「モーセが十戒を授かった山」と確かに言っているんですよね。だからシナイ山に間違いはないと思います。 下記の図は、アイシス(赤)、キャロル(ピンク)、メンフィス(緑)を推定したのですが…  モーセが十戒を授かったシナイ山はシナイ半島の突端に近い位置。
モーセが十戒を授かったシナイ山はシナイ半島の突端に近い位置。アルバの谷…アラバ渓谷の事だと思うのですが、こちらは死海からアカバ湾までの間でかなりの距離(150kmぐらい)の区間をさします。が、「今夜」アルバの谷に野営するメンフィスへ、死海(塩の神殿)に居たアイシスが夜這いできる距離だった訳なので、アラバ渓谷のかなり死海に近い部分だと推測できます。 一方のキャロルはナイル下流から陸路でムサの山へ向かいます。マシャリキがムーサの山がもう間近であるという事を言っていますから、シナイ半島の中に入った事は間違いありません。 アルバの谷を出てエジプトに帰還するメンフィス、同行するカフラー暗殺に赴くアイシス、もうすぐムサの山に着くキャロルがお互い気づかずに一同に会する訳ですが、その場所はというと… アイシスとメンフィスが居る位置は元々近いのですれ違いは可能。 エジプト軍が来るという時にマシャリキがキャロルに「アルバに谷はずっと東…エジプトへの帰路は対岸を通る」という言い方をしてます。 シナイ山近くから見るとアルバの谷は東ではなく北(細かく言うと北北東)。アルバの谷の西側でシナイ山が間近に見える場所というのはありません。。しかも周囲の山は何故か木が生えている。死海〜アルバの谷ぐらいは行っていますが、シナイには行ってないのですが、百科事典によると「丘陵性の砂漠が大半を占める」そうなのですが。(レバノン杉の様な例もあるので、砂漠化していなかった可能性もあります。) メンフィスの経路はアラバ渓谷に陣をはっているので、地中海方向に向かって帰路を取る事になります。 キャロルの場合、ナイル下流のどの辺りで出現したのかが不明ですが、通常(採掘隊の場合)はシナイ半島のスエズ湾にそって進むのですが、そのルートを取ると、アルバの谷からエジプトに戻るメンフィスとの接点がなくなります。さわざわざメンフィスがシナイ半島をぐるりと回るとも思えませんし。 従って、キャロルを一度死海方向に進ませたのですが、ムーサの山が見える位置に彼等が来るとすると、メンフィスが地中海沿岸コースを取ると遭遇しません。この為、シナイ山の方に一度Uターンし、砂漠地帯を横断してエジプトに戻ったという危険なルートを考えてみましたが…  と、ここまで書いて更に混乱をかける方が登場しました。イズミル王子です。(笑) と、ここまで書いて更に混乱をかける方が登場しました。イズミル王子です。(笑)レバノン山中に居た王子がムサの山に行くのに 「塩の海(死海)の道をさけて、 大きくアラビア砂漠を迂回し… エドムの地からムーサの山に入る」 と言っています。 という訳で、王子のお言葉通りに経路を書いてみました… (..;)あ・・・あれ? アラビア砂漠を迂回するという事はエジプトの国内を通る事であって… 王子、アラビア砂漠とシリア砂漠間違えていませんか? まぁ砂漠は、王子の勘違い又は、古代では現代とは異なる呼び方をしていたとし、シリア砂漠を迂回…するとユーフラテス川の方に行くことになるから凄い移動距離になっちゃいますけど、ぐるっと回ればエドムには確かに行けます。 所で、ナイル下流から直線でもシナイ山までは200km以上あります。キャロルを上述の様に地中海沿岸を通る経路にすると、移動距離が500kmになります。その後、レバノン杉のある(オロンテス河付近)までシナイ山からおよそ600km。飛行機も車もない時代ですから、この移動距離は妊婦のキャロルには相当な負担だったと思うのですが…。  個人的にはキャロルが居た麓の村の様子から、シナイ山でなくネボ山(モーセが亡くなったとされる、死海近くの山)だと、メンフィスやアイシスとの遭遇もしやすいし、レバノン杉の山中にも比較的近いし話が成り立ちそうなのですが… という訳で、勝手にシナイ山をネボ山に設定してみました。 アイシス(赤)、イズミル王子(黄緑)、メンフィス(深緑)、キャロル(ピンク)です。 王子とキャロルの身体の為には移動距離も少なく、良いルートだと思うのですが…(笑) 王子がエドムに行っていませんが、シナイへ行かないので、わざわざ遠回りすることもないでしょう。 それにエドムは都市名ではなく、死海の南側一体を指すので、エドムと呼ばれる部分を通ったとも思えます。 もう一つ理由があります。 ミノアの面々がキャロルをさらえた場合、地中海沖合にまつユクタス将軍の所に連れていくと思われますが、彼等は徒歩。 シナイ半島の突端から地中海まで、200km近くの大移動では誘拐?するにはかなり大変かと思います。 ネボ山であれば、地中海までおよそ100km。 さて、どうでしょう? 騎馬・乗馬 馬に乗るのはペルシア統治以降という事なので… 騎馬に長けたのは前9世紀頃成立したとされるメディア王国(しっかり出てきていますが)ですが、新王国時代とは時間的に隔たりがありますし、もし騎馬が伝わるとすれば、黒海沿岸のスキタイ(こちらも時代的にはかなり離れていますが)からの方が確率は高い気がします。 スキタイの特徴は鐙(足をかけるところ)がない乗り方ですが、カルナック神殿に外国人らしい人物が馬に乗っている壁画がありますが、やはり鐙がありません… 駱駝 古代エジプトでは駱駝を表す言葉がありません。 壁画類も馬と違って一切ないため、駱駝はペルシア時代に入ったと言うのが定説になっています。外国からの商人が持ち込む可能性もあるとは思うのですが、珍しければ多分壁画などに描いた筈ですし… 仮に存在していても、描くのも嫌うほど忌みな動物であれば、それに身分の高い人達が乗る事もありえないのでは… ベッド 寝室の風景が良くあるので(笑) 古代エジプトのベッドは足の方に板があり、頭の方は何もありません。つまり、今のベッドの逆。頭の部分はリクライニングベッドの様にやや起きあがっています。 いつ見ても、足の方に板がある様な作りには見えませんが… 枕は日本の箱枕みたいな固い物が出土品では多いようですが。 緑のアイライン 緑色(孔雀石など)のアイラインは古王国時代の特徴となっています。新王国時代は鉛鉱石の黒。プトレマイオス朝では下が緑で上が黒だった 説もあるので、趣味の問題 と片づける事も可能でしょう… 尚、孔雀石を砕くと青い粉末になるらしいです。(アクセサリーとして持ってはいますが、勿体なくて砕けないです) リビア人 リビア人にはいくつかの呼称がありますが、ヘチェヌと呼ばれるリビア人は金髪碧眼。まさにキャロルそのもの。 これはエジプトとクレタの交易がアフリカ大陸の対岸に当たるキュレネ(現在のリビア付近にある古代のフェニキア人都市)へ船で渡り、そこから陸路でエジプトに来たため、クレタ…又はギリシア系の人を指すのだとは思いますが… カーフラ王女がキャロルの事見ても何とも思わなかったのは、本国では金髪の人間が珍しくなかったから かも知れませんね。 それから、定説(クレタとの交易ルート)が正しいとすると、ユクタス将軍が船でナイルを遡のぼってくるのは超珍しい事になります。というか、ナイル自体は長いけど幅は狭いし、深さもそれほどない…確か2mぐらいたいだから、大きな軍船が何隻も入ってこられるものやら…(特にシュムウ)。 エジプトが海軍を持つのはネコ2世がB.C.610頃ギリシア人の傭兵を使ったのが最初という事のようです。(エジプト人の航海術は陸沿いに行く方法だった) ちなみに、このネコ2世は古代のスエズ運河として、紅海とナイルのペルセウム支流を運河で結んでいます。でも、ペルセウム支流は新王国時代の末期に干上がったと書いた本もあるので…(カノプス支流とペルセウム支流が、現在はないのは事実。) 奇っ怪な都市群 まず、タニス。古代エジプト名はジャネト。末期王朝の第21王朝に建造された都市です。 ・・・新王国時代には一応存在しません。 そして22巻P176の地図を見てください。一番シナイよりの支流に沿って タニス がありますが、どうもナイルの支流を1つ間違えて描いてあるようです。ペルセウム支流がある新王国時代なら、あるとすればもう1つ内側です。 この地図のタニスの描かれている位置は、ヒクソス時代の首都アヴァリス、新王国時代だとセティ1世が起工しラムセス2世が完成させたペルラムセスがある付近になります。 そして、砦のあるカナン地区のサマリア。 サマリアというのは聖書の列王紀伝の16章によると、オムリ(バビロニアの大臣ではなく、イスラエル王)がサマリという人から買った山の上に築いた都市 という事になっています。(聖書を読んでいて気づいた) このサマリアはイスラエル王国の首都(ユダ王国との分裂後のです)で年表で調べると、B.C.887年の事。新王国時代からはほど遠いし、新バビロニア、ペルシア時代はエジプトの国力も落ちていて、カナン地域はこれらの国が統治していたわけですから、エジプトが砦を築くことが出来るとしたら、その後のプトレマイオス王朝時代ぐらい。 又、ミタンニが使者が来た程度で出てこないのも不思議な事です。(使者が出てこなければ、ヒッタイトが滅ぼした後だと思っていたんだけど…) そういえば、使者が来るティロはツロの事だと思うのですが(描かれた衣装が他のフェニキア人に近い)、最初はツロでしたね。スペルだとTyreなんですが、ティルだったり、テュルだったりカタカナの表記も本で違うので、地名(人名も)は一番困ります。ちなみに、エジプトと紅海の間の地域を「メディア」と呼ばれていたりする資料もあります。またプレヒッタイトのあった所にエディアという集団が居たことも解っています。(紛らわしい) 解読されていないヒッタイト文字 3巻に出てくるこの事は、楔形文字で書かれた方のヒッタイト文字ではなく、スミュルナ(現イズミル)、カルケミシュ、ハマトで見つかった ○や△の様なで書かれた記号の様なヒッタイト文字方ではないかと思われます。というのは、漫画が連載始まる以前に楔形文字のヒッタイト語は解読されていますので。 この○△の文字は、1949年にカラテペでフェニキア語との対訳碑文が出たという記事が1989年の刊行本に出ているのですが、解読が出来たのかどうかが手持ちの本では見つかりませんでした。 ちなみにこの文字は、ヒッタイト語ではなく、ルゥイ語だそうです。(ヒッタイト自体はシュメール語、アッカド語、ルウィ語、パラ語、原ハッティ語、フリル語の6言語を使う国家。今のインドみたいな感じかな?)出土地帯から、ヒッタイト新王国ではなく、滅亡後のシリアなどに散在したヒッタイト小王国群の頃じゃないかとも思われますが… 一人の宰相 宰相(チャティ)は第18王朝から上エジプトと下エジプトに二人置かれていたという事が分かっています。(但し、末期王朝時代になると宰相職も消えてしまう)ここでは、イムホテップ一人しか見あたらないようですが… メンフィスが即位した時には国外に居た様なので、それで良いのか? とも思ったりもして…。 又はイムホテプは上エジプトの宰相で、下エジプトの宰相は、実はアイシスだったりして?(あの支持基盤の強固な状態だと、先王の頃からかな?) クレタの遺跡 22巻でジミーとブラウン教授が発掘した(ってエジプト学とは少し畑違いな気もするけど)クレタの遺跡の説明がありますが、実際のクレタの地下室からは、人身御供の人骨に肉をナイフで削りとった痕跡がある多数の子供の骨が出た だったと思います。肉を削り取った跡から、食人があったのでは?というものでしたが… 古代エジプトには炭はないわっ 30巻P72 あります (^^; .... 古代エジプト語では、ジュアー・トと呼びます。勿論木炭です。 29巻P205で「…医学エーベル・パピルスがあったわね」と言っている、そのエーベル・パピルスにちゃぁんと炭の使い方が載っています。 最も、使用方法は、排出物(膿とか)の付着に使っています(日本でも生薬として使うときに同じ使い方をするそうです。)ので、侍医の方は解毒作用を知らなかった可能性はあるかと思いますが。 備長炭の様な炭ではないとは思いますが、「炭の粉を水に浮かせて」使うには十分だったと思えるので、あーゆ〜せっぱ詰まった状態の時は、周囲の人にとりあえず、あるかどうかを訪ねた方が良かったのでは? 鉄の鉱石はでないのかしら ねっ 45巻P137 古代書ではエジプトは鉄を産出しなかったってあるけど 同P138 鉄は一応あるんですけどね。製鉄出来る鉄鉱石では無いですが。 ほお紅や薬に使っていた黄土(酸化鉄、セチュ)、竜の血(デュトュ)と呼ばれる赤鉄鉱、セトの骨と言う磁鉄鉱(磁石)とか。 となると、(記録としては見つからなかったけど)世界中のどの鉱山にも出る という黄鉄鉱もあったのでは? 黄鉄鉱は硫酸を取った後は鉄鉱石として使えるそうです。 鉱物技術は良く分からないけど、酸化鉄からも鉄を作れたらしいですが… 鉱物マップを見ると、第1急湍付近で鉄のマークがあります。と言っても鉱物学の世界だから、考古学を専攻していたキャロルは知らないのでしょう。それに、ヒッタイトでも鉄器を大量生産出来るほどではまだ無かったので、鉄が見つからなくてもまだまだそれほど問題にはならないでしょう。 尚、一連の話の中に新しい鉱脈から「ラピスラズリなどが産出すれば…」という発言もありますが、出れば嬉しいって事で。 ラピスラズリ(ケセベジュ)は特殊な条件下で出来るので、産出場所が限られています…というのは古代の人は知らないですからね。(キャロルが発言していたら問題発言だけど)。 これ キャベツ なのっ 46巻P174 実際の古代エジプトの記録ではキャベツではなく、レタスは記載が多いのですが… 壁画だったら、レタスもキャベツも大差ないとは思いますが。(笑) 一応、キャベツはケルト地方原産でB.C.600年頃地中海に広まり、葉キャベツ(つまり丸くならない)で観賞用だったそうです。結球(玉状になる)するようになったのは今から1000年ほど前つまり、紀元1000年頃から。 キャベツは暑さに弱く、、育成温度は15〜20度。(それ故、日本では高原キャベツなるものがある) う〜ん、エジプトの何処でキャベツを作れたんでしょう。(冬なら可能かな?)そして、近代?になって結球するようになったとされるキャベツがどうして古代で結球していたのか… 謎です。(笑) 死海に沈む… 謎の1つとして書籍でも取り上げられているようですが。(笑) まず、死海の周囲。 実際に死海に行くと、確かに周囲は切り立った崖…というより、死海自体がカルデラ湖のように周囲からずっと窪んだすり鉢状態。湖はそのすり鉢の底の所にあります。下に降りると、海岸の砂浜のような部分が湖の周囲に広がっています。湖の中も入った感じから、周囲は浅い(中央の深さは不明)ので、周りがぐるりと囲まれた砂浜のある海岸と言った所でしょうか? 勿論、死海の真中(?)には現在国境があるため、ぐるっと1周したわけではありませんから、見えた範囲でのコメントですが。 つまり…マンガのような岸壁に水が打ち寄せるような状態ではありません。ただ、3千年以上前の話だから、水量が豊富で崖部分まで湖が広がっていた可能性もありますが。 死海を泳ぐ。 沈んでしまった(!)キャロルを助けるため、ウナスやルカが死海の中を泳いでいますが、浮く、浮かない以前にかなり凶器の沙汰です。 というのは、死海の水は「ものすごくしみる」のです。 死海に行った方は分かると思いますが、手足は大丈夫ですが、顔に水がちょっと掛かっただけで、酷い火傷をしたかのような、ヒリヒリとした凄い痛みを感じます。面の皮は厚い筈の私でもわずかにはねた数滴の死海の水が頬にあたっただけで、死ぬほどの思いをしました。(笑) 海の比ではありません。おそらく、眼を開けては居られないはずです… 最も、忠誠心の賜物かもしれませんが。 沈む? 本当に死海では人は本を読んだ状態でも(つまり手足に若干の力を加えても)軽く浮きます。でも、水中ウォーキングばりに歩く事も可能なので、全てのものが完全に浮いてしまうわけではありません。 絵からするとかなりの高さなので、一度重力の力の強さで沈んで、その後は浮く可能性が高いでしょう。それよりも、現在の死海の状況から、湖の周囲は決して深いわけではないので、浮く前に落ちた時点で底にぶち当たる可能性が大きいと思いますが。 もう一つ考え方があります。 あの絵(崖まで水がきている)から判断すると死海の大きさ自体が現在の数倍あったように見受けます。となると、現在ほど塩分が濃くなく、通常の海水程度の濃度だったので沈んだ という考えもできます。 岸辺の神殿 新王国時代(には思えないのだが)として、年代によっては死海周辺もエジプトの属領であったのは確かですが、エジプトの神殿があったかどうか…。 (あの周辺で、ヒッタイトの遺跡を偶然見ましたけど) カナン付近の出土物を見ると エジプトかぶれ とでも言うべきか、エジプト風の小さな神像などが多数出ているようですが、地神であるバアル神の他、メソポタミアの(エンリル神やイナンナ女神)の方は大きな像もあり、そちらの方が多いようです。 塩の神殿がどの神を祭っていたのかが分かりませんが、もし、神殿があったとしたら、カナン・エジプト・メソポタミアの神の混合状態でエジプトの神殿ではあり得なかったったのではないかと…。 アムドゥアトの神 初めの方に良く出てくるのですが、アムドゥアトの書に出てくる神々(ラー神?)を指すかと思うのですが、メンフィスの墓所の呪いの文は解るのですが、アイシスがやたらに口にするのはどうかと。 ドゥアトという単語が冥界の事だと分かりました。とすれば冥界の神々。アムドゥアトの書ではラー神など。 冥界の神に祈るのは「死者のその後」の方が向いているかと思うのですが。 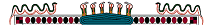 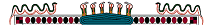 王家の紋章 細川智恵子 秋田書店 |