 | (旧約)聖書 | 
|
|---|
|
西洋人の古代エジプト好きはこれから始まったのでしょう。 始めて読んだのは幼稚園の時。カトリック系の幼稚園へ通っていたので、私か姉が誕生日にでも貰ったものか、日曜学校で貰ったものかと思います。 かくいう私は、小学生時代は毎日曜には日曜学校へ行くほどの人間でした。とはいっても親の実家には仏壇と神棚はあったし、神社仏閣では偶像(私的にはキリストの磔刑像も同じだと思うのですが)をちゃんと拝んでいましたし。 ただ、数ある宗教のなかで、キリスト教だけがきちんと聖職者から教義を教わった宗教であるのは間違いありません。 でも、一神教は理解できない。(笑) 尚、ここで取り上げるのは 聖なる書 としてではなく、民話とか神話とかと同等の扱いなので、ご理解の上ご覧下さい。
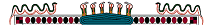 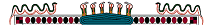 聖書の矛盾点などがある事から複数の話、年代をまとめたものと言うことになっています。元々口承されていたものをまとめた物とされて、分析された形式としては ヤーウェ資料…神の名前がヤーウェ。B.C.900〜700年にユダ王国で書かれたもの。 エロヒム資料…神の名前がエロヒム(途中でヤーウェに変わる)。分裂後のイスラエル王国で書かれたもの。 申命記資料…ヨシヤ王(B.C.621年)宗教改革時のもの 祭司的資料…バビロンの捕囚時代。 現在目にする『聖書』は紀元後900年頃の当時の写本が元になっているそうですが、死海文書(B.C.100年前後とされる)との差異はあまりないとの事。 時代は下りますが、日本では、稗田阿礼が暗唱した帝紀(天皇の系譜、年代記=聖書で言うと列王紀や歴代志?)と旧辞(伝承されていた神話、伝説=聖書で言う創世記、出エジプト記?)をまとめて『古事記』を作った例があるので、そのような感じでしょうか? 歌もあるので、聖書で言う詩編と似たような。日本の場合は、同時期に『日本書紀』があります。こちらは古事記の正説に対して諸説が併記されているので聖書の外典や偽典と呼ばれるものに近いのかも。 聖書の場合、口承の物を文書化した際、矛盾点は直さなかったようですが。 洪水伝説をはじめ、メソポタミア地方、古代エジプトなどと類似点を比較されています。(当初定住していた訳ではないので)それらの国で得た話しなどを取り入れていったのでしょう。アッカド、バビロニアにはシュメールのヒッタイトの神話にバビロニアの話が入っているのも同じようなものかと思います。最も、洪水伝説は世界各国にありますが。バビロンの捕囚時代に書かれたものもありますからバビロンの影響も大きいかもしれません。 ユダヤとは? 辞書を調べると、 1.セム族の一派、アラム族の一つでアモライト・ヒッタイト・フィリスタインと混血して成立。 2.ユダ王国の住民。ユダ族。 3.バビロン捕囚後ユダの地に住んだ民。 4.ユダヤ教徒 2はユダ王国だけを指すとなると、もう一方のイスラエル王国も調べないといけません。 イスラエル王国は、「旧約聖書」で、ヤコブの子一二人に始まる一二部族の名。セム系の遊牧民で、パレスチナからエジプトに移住。ユダヤ人。ヘブライ人。 イスラエルの場合、分裂後の国家の民を指すわけではないようですね。 民族的には小アジア系の血が入って、言語学的にも印欧語族ではない民族。 という事になりそうですね。 国家としては、死海周辺ですが、この辺りは小国家−エジプトの属州−などがあったので、その中の一つになるのでしょう。 聖書の中の古代エジプト 奴隷としてエジプトへ(兄弟達に)売り飛ばされ後に宰相となったヨセフ、その後のモーゼは在エジプトなので、この辺り(創世記37章以降、出エジプト記)はエジプトについての記述となります。 出エジプト記はラムセス2世の治世頃と推定されています。(出エジプト記第1章にラメセス(ペル−ラムセス)の建設について言及されている)、編纂された時の時間差故か、後の列王紀(上14章)でシシャク(シェションク)王(下2章)ネコ(ネカウ2世)王の名前が載っているのですが、出エジプト以前はファラオの名前は出てきません。 実際に古代エジプトに現れるイスラエル人 第2中間期、ヒクソスの王朝の中に ヤコブレフ というユダヤ系(当時ならカナン地方の民族名)の名前があります。 でも、普通にエジプトの神々を信仰していたようです。即位名はメル・ウセル・ラーですから。 メルエンプタハのB.C.1207年の日付の入った石碑の中に「イスラエルは荒らされてその種はなく」との記述があり、古代エジプトでイスラエルが登場する最初の例となっています。 シェションク(聖書ではシシャク)のパレスチナ遠征はカルナック大神殿の壁画に。 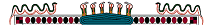 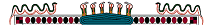 簡単な経緯(宗教を一切抜いて今風に) カナン地方の飢饉等でエジプトへ難民として流れ込み居着く。それ以前も商売などで入っていたでしょう。 難民が大量であれば、手に技術があってもその仕事につくのは難しいですし、又、土地がない(元々遊牧民ですが)のと、エジプトの耕作地は周囲が砂漠なので開拓するのも難しいため、農民になるのも難しい。となると、日々の糧を得るのに建設現場での肉体労働は一番手っ取り早い方法。特に当時は銀行もありませんから、給与(パンとビール)では貯蓄もできません。(物々交換はしたでしょうけれど)となると、ある程度、場合によっては毎日働かなくてはいけない…(古代の記録ではズル休み?もあったみたいですが) 当時は重機もない人力頼みの建設現場。3Kの仕事をしていると嫌になるので、かつていた土地(相当伝説的に美化されていた?)に戻ろうとモーゼというリーダーとともに現場を脱走した。 こんな感じでしょうか? 民族移動がよくある時代で、しかもそのために滅びる国まであるわけですが、大量難民?を受け入れ出来た古代エジプトの包容力も凄いものです。 苦役と食生活について  後のヘロドトスでさえ、ピラミッド建設をファラオの悪行の様に記述しています。ピラミッド建設と彼のエジプト訪問との間の年代差からそう捕らえられても無理はないかも知れません。ちなみに、聖書にはこのピラミッド(高層建築のない当時は、絶対目立つ筈なのだけど…)は出てきません。彼等は主にデルタ地帯に居たはずなので、目にするチャンスはあったとは思うのですが。 後のヘロドトスでさえ、ピラミッド建設をファラオの悪行の様に記述しています。ピラミッド建設と彼のエジプト訪問との間の年代差からそう捕らえられても無理はないかも知れません。ちなみに、聖書にはこのピラミッド(高層建築のない当時は、絶対目立つ筈なのだけど…)は出てきません。彼等は主にデルタ地帯に居たはずなので、目にするチャンスはあったとは思うのですが。苦役は「倉庫の街ピトムとラムセスを建てた[出エジプト記第1章]」があげられていますが、この時代は、ピラミッド建築の様な何トンもある大きな石を運ぶわけではなく、それよりずっと小さな石のブロックを使っていました。 左図の様な柱も石のブロックいくつも積み上げて、綺麗に削って作った物です。勿論、オベリスクのように1本物もありますが。 こういう事をしていると、大変かな?と思うのですが、「漆喰こね、煉瓦造り、および田畑のあらゆる努めにあたらせ…[出エジプト記 第1章]」 普通の労働じゃないんでしょうか…(笑) 飢えているときは、働いて食料が手に入ることで満足しますが、今度食料が事足りるとなると、職場の環境(3K)に文句を言いたくなるわけです。 イスラエル人のエジプトを出た後の民のわがままぶり(故に私はモーゼは十悔−10回は後悔した−と思う。)を聖書で読むと、エジプトでさして悪い待遇じゃないのに文句言っていたのではないかと思ってしまいます。 というのも、出エジプト後にイスラエルの民は 「われわれはエジプトの地で、肉の鍋のかたわらに座し、飽きるほどパンを食べていたとき…[出エジプト記 第16章]」 とモーセに文句を。私にはすき焼きを囲んでいる面々が浮かんでしまうのですが… 肉鍋の量は分かりませんが、飽きるほどパンは食べていたんですね?(笑)苦役の見返りはちゃんととあったんですね。 尚、近代…になってしまいますが、例えばメキシコの先住民族は4〜50年で人口が1/5に減っています。勿論、強制労働の他に彼の地になかった伝染病や故意の殺戮もありました。所が、古代エジプトのユダヤ人は「しかし、イスラエルの人々が苦しめられるにしたがって、いよいよ増え広がるので…[出エジプト記 第1章]」増えているって事になってますよね…。食事の与えすぎ?労働が甘すぎた? 追記(2003.06.15) 何気なく、スエズ運河についてを読んでいたら、当時働かされたエジプト人達は無給で、犠牲者は12万人だとか。 モーゼについて 男子を殺す様に言われた為、川に流されたモーゼはファラオの娘に拾われて育てられる分けですが、彼がエジプトを出た理由は「同胞の所に出て行って、その激しい労役を見た。彼はひとりのエジプト人が同胞のひとりであるヘブル人を打つのを見たので、左右を見回し人のいないのを見て、そのエジプト人を撃ち殺し、これを砂の中に隠した。(中略)モーセは恐れたあのことが知れたのだと思った。[出エジプト記 第2章]」 人が居ないのを確認するとは確信犯ですね〜 その前に打たれた理由を確認すべきだったのでは? もしヘブル人に方に非があった可能性もあったでしょうに…。そして、『雄弁な農夫の物語(中王国時代)』で官吏に物品を奪われた農夫が裁判に訴え出る という事が可能な国だったのですから、きちんと出るところに出るべきでは? 十の災い。 モーゼたちが災いを起こすと、エジプト側の魔術師(神官でしょうか?)も同じ事をするんですね。蛇は出すわ蛙も出すわ。 普通、消す魔術をしませんか? 増えたら困るものを更に増やしてどうするの?(笑) エジプトに神官がエジプトの神の力で魔術を使ったとすると、何も出来ない神 とは聖書を書いた(伝えた)人は思っていなかった様ですね。 災いの中に最後の術が日食だったので、日食の日を調べてみました。最近は自転の速度の変化とかで実際の公式とは違う歳月が出るらしいんですが、出エジプトの推定年付近だと B.C.1261.4.14 17:26(途中日没) B.C.1257.7.27 9:48 B.C.1250.09.07 8:51 B.C.1246.12.10 10:46 出エジプトは、ラムセス2世時代頃というので、この辺りの皆既日食(もしくはかなり皆既に近い部分日食)を計算してみました(EMAP.EXE Ver2.32使用)。場所はメンフィスで計算。部分日食はもっとあり、部分日食を含めると実は結構毎年のように日食があるんですね、エジプトは。近年も何度かあるようで日食鑑賞ツアーなんかを募集しているのを見ました。 だから太陽が隠れたぐらいじゃ珍しくない? いざ、約束の地へ? 下の地図を見てください。  苦難な遠回りをしたのは、ホルスの道(ピンクの部分)を回避するためだと思われます。エジプトの要塞が道沿いに点在していますから。 今はスエズ運河で地中海と繋がっている紅海ですが、そのスエズ運河付近は当時は湖が点在する地帯(末期王朝時代には干上がった巨大な塩湖があったそうです)。古代の地名からたぐると出エジプトのみなさんがペルラムセスを出てシナイに向かった際の通り道にあるのは、紅海でなく、近くに点在する湖。しかも、ヘロドトスの頃は紅海の事をアラビア海と呼んでいたそうなので、聖書の原文がどう表記しているのか定かではありませんが、どう見ても紅海を渡ってないんですよね! 沼地へでも逃げたのでは? ファラオ一行は服が汚れるのが嫌で引き返したぐらいだったりして… 尚、『ウエストカー・パピルス』には「スネフル王をの気晴らしのためジャジャ・エム・アンクが美しい娘に船を漕がすという事を提案。その有様を見て王が楽しんでいた所、指揮を取る娘が新しいトルコ石の魚形のイヤリングを落とし、漕ぐのをやめまてしまい、ファラオに呼び出されたジャジャ・エム・アンクは呪文を唱えて、池の水の半分をを他の水の上に重ね、水の底の石の上にあったイヤリングを取りに行き、娘に返しました。12キュービット(約6m)の深さだった水は24キュービット(約12m)になっていました。彼はまた呪文を唱え水を元に戻しました。」という部分があります。 この物語のパピルスは新王国時代のものですが、文体から古王国(第12王朝 B.C.1900〜)頃、またその口承があったとするともう少し遡れるとされています。紅海の水が裂けるシーンと酷似してますね。 ポテフルの妻とヨセフの話も『二人の兄弟』にも類似点があるという指摘があります。 エジプトに居た時耳にした話が混じっていませんか? 追いかけてきたファラオ一行 「えりぬきの戦車600と、エジプトの全ての戦車…[出エジプト記 第14章]」 全ての戦車を連れくるなら、て別にえり抜きも何もないんじゃ… 「パロのすべての馬と戦車および騎兵と軍勢は… [出エジプト記 第14章]」 国語辞典では騎兵は騎馬の兵とあるのですが、エジプトではペルシア統治以前は騎馬の習慣は無いことになっております。はい。 やはり、聖書成立年代からしてペルシア以降の話と混ざってしまったのでしょうか… 個人的には第18王朝成立の際の、ヒクソス(カナン系の民族)の追放何かも土台にあった気がします。 年代 考古学的資料はないけれど、ラムセス2世の治世で起きたであろう という事になっています。 モーセが再び戻ってきたのは80歳、エジプトを出た時の年齢が分かりませんが、まだ若い頃のようなので、ラムセス2世の治世は約66年(92歳ぐらいで没)とされているので、ラムセス2世が出エジプト時に(溺れないにしても)仮に死んだとすると、モーゼを拾った王女はラムセス2世の娘の可能性は低いかと思います。 海外の説の中には末期王朝の頃をあてているものもあります。 尚、バビロンの第2捕囚の後、 「バビロンの王ネブカドネザルはユダの地に残しとどまらせた民の上に、シャパンの子アヒカムに子であるゲダリヤを立てて総督とした…(中略)…7月になって王の血統のエリシャマの子であるネタニヤの子イシマエルは十人の者と来て、ゲダリヤを撃ち殺し、又彼と共にミヅバにいたユダヤ人と、カルデヤびとを殺した。そのため、大小の民及び軍勢の長たちは、みな立ってエジプトへ行った。…[列王紀 下第25章]」 さんざん苦労して出てきたエジプトに又戻っちゃったんですね… 個人的には、出エジプト記は、新王国開始時のヒクソス追放(ヒクソスはカナン地域から入り込んだ諸民族の総称と言われている)、アテン信仰者(いわゆる単一神信仰)の迫害、そして、ラムセス2世時の(追放か逃亡か)体験や伝承が混じって出来た様な気がしますが。(あくまでも想像)。 奇妙な類似 別項でヘロドトスの『歴史』を取り上げていますが、それと聖書の関連を 「それゆえ、主はアッスリヤの王について、こう仰せられる。 『彼はこの街にこない、またここに矢を放たない、盾を持ってその前に来ることなく、また累を築いてこれを攻めることはない。彼は来た道を帰って、この町に入ることはない。主がこれを言う。私は自分のため、又私のしもべのダビデの為にこの街を守って、これを救うであろう』 その夜、主の使いが出てアッスリヤの陣営で18万5千人を撃ち殺した。人々が朝早く起きてみると、彼等はみな死体となっていた。アッスリヤの王セナケリブ(※センナケリブの事)は立ち去り…[列王紀 下19章]」 「後になってサナカリボス王(※センナケリブ)がアラビアおよびアッシリアの大軍を率いてエジプトに来攻したが、エジプトの兵士達は王に救援することを肯んじなかった。(※この文章の前に、軍人の特権の土地を王が取り上げた事が言及されている)祭司である王は困惑し、内陣にはいると神像に向かい、自分が蒙るべき悲運を嘆き訴えたのである。祭司は嘆きつつ何時しかまどろむと夢を見た。神が彼の傍らに現れ、敢然とアラビア軍に立ち向かえば、自分が援軍を送ってやるから、決して不幸な目に遭うことはない、と激励してくれた夢である。王はこの夢のお告げに信頼し、彼に従う志のあるエジプト人を率い、エジプトの入り口にあるペルシオンに陣を構えた。彼に従った者の中には一人の兵士もなく、全て小売り商人や職人、それに市場で生業を営む者達などばかりであった。 さてエジプト軍がこの地の達した後、夜になっての鼠の大群が敵陣を蔽うばかりに押し寄せ、その箙、弓、さらには盾の把手まで囓り潰してしまい、翌日敵は丸裸のまま潰走したため多数の戦死者を出すことになった。[歴史 巻2 141]」 この話、詩編104章とアテン賛歌がより、内容的には似ているというか殆ど同じ様ですね。最終的には戦死したようですが、武器を取り上げる?エジプトの神の方が寛大?それともその後悲惨な目に遭うから残酷? 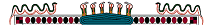 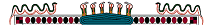 日本聖書協会 ※歴史の資料とするなら解説があるものの方が分かり安いかも知れません。 「上は天にあるもの、下は地にあるもの、または地の下の水の中にあるものの、どんな形もつくってはならない。 [出エジプト記 第20章]」 「2つの金のケルビムを作らなければならない。(中略)ケルビムは翼を高く述べ、その翼を持って贖罪所を覆い、顔は向かいあい… [出エジプト記 第25章]」 ケルビムというのは羽が6枚の天使だったと思うのですが、天使だから天にあるもの じゃないんでしょうか… ストカーのドラキュラを読んで気づいたのですが、ドラキュラの苦手な(私が偶像じゃないのか?と思う)十字架ですが、この本の中…イギリス人つまり英国国教会の人が十字架を偶像崇拝の と言っているのに驚きました。 キリスト教は宗派も様々あるので、違いは確かにあるのですが。 |